
デジタルマーケティングの施策の一つとして、自社で所有・運営するオウンドメディアの重要性が高まっています。しかし、質の高いコンテンツを作成するだけでは、十分な成果を得ることは難しくなってきました。
効果的なSEO対策を組み合わせることで初めて、オウンドメディアは真価を発揮します。本記事では、オウンドメディアのSEO対策について体系的に解説し、集客力と顧客獲得率を向上させるための具体的な手法をご紹介します。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
オウンドメディアのSEOとは
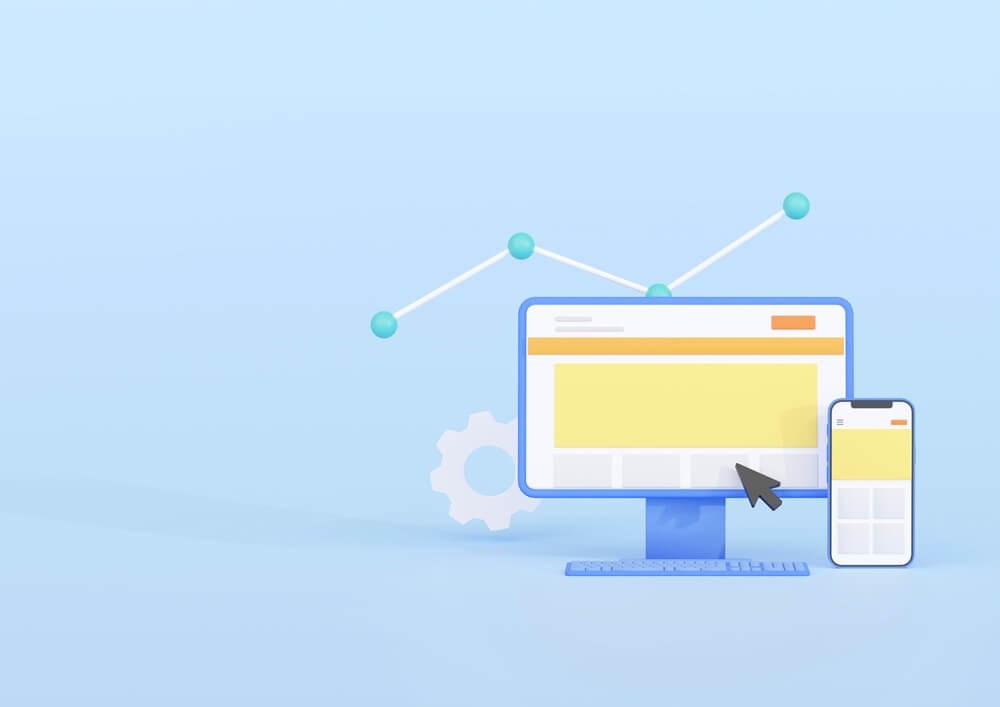
オウンドメディアのSEOとは、自社が所有・運営するWebメディアを検索エンジン最適化することで、Googleなどの検索結果で上位表示を目指す施策です。
一般的なSEO対策と基本的な考え方は同じですが、自社ブランドや製品・サービスに関連したコンテンツを継続的に発信するという特性があります。
なぜオウンドメディアのSEO対策が重要なのか
オウンドメディアでSEO対策を行う最大の意義は、長期的かつ安定した集客基盤を構築できる点にあります。一度検索上位を獲得したコンテンツは、その後も継続的にアクセスを集め続けるため、時間の経過とともに蓄積されるアクセス数は非常に大きなものになります。
広告のように、予算がなくなれば集客も止まるといった心配がなく、一度の投資で長期間にわたって効果を得られる点は魅力的です。
リスティング広告などの有料広告と比較すると、初期段階では効果が出るまでに時間がかかるものの、中長期的に見れば圧倒的なコストパフォーマンスの差が生じてきます。
オウンドメディアのSEO対策で期待できる効果
オウンドメディアにSEO対策を施すことで、以下のようにさまざまな効果が期待できます。
| 効果 | 具体例 |
|---|---|
| 検索流入増加 | • オーガニック検索からの訪問数向上 • 検索順位の改善 • 新規ユーザーの獲得 • 長期的な流入の安定化 |
| コンバージョン向上 | • 資料請求数の増加 • 問い合わせ数の増加 • 商談機会の創出 • 購買・契約率の向上 |
| ブランド認知度向上 | • 企業認知度の向上 • ブランド信頼性の構築 • 業界での専門性確立 • メディア露出機会の増加 |
オウンドメディアのSEO対策を行うことで得られる最も直接的な効果として、検索流入の増加が挙げられます。また、SEOによって獲得した見込み客は、すでに自社の提供する情報に価値を見出している状態であるため、契約に至る確率が高まります。
ブランド信頼性の構築も見逃せない効果です。E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識したコンテンツ作りを行うことで、Googleからの評価だけでなく、ユーザーからの信頼も獲得できるでしょう。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
オウンドメディアの運用方法

オウンドメディアを効果的に運用するには、明確な目的設定から始め、適切な運用体制を構築し、計画的な更新頻度と品質管理を行うことが重要です。具体的には下表のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①目的設定 | • リード獲得(資料請求・問い合わせ獲得) • ブランディング(認知度向上・専門性アピール) • 採用強化(求職者への情報発信) • 顧客育成(ナーチャリング) |
| ②運用体制の構築 | • 社内運用(専任チームの構築) • 外部委託(SEO会社・制作会社への依頼) • ハイブリッド(社内外の協業体制) • フリーランス活用(個別契約) |
| ③更新頻度の策定 | • 週次更新(1~2記事/週) • 月次更新(4~8記事/月) • 季節性コンテンツ対応 • トレンド対応の臨時更新 |
| ④品質管理 | • 編集ガイドラインの整備 • 専門家による監修体制 • 校正・校閲フロー確立 • SEOチェックリストの活用 • 定期的な品質レビュー |
オウンドメディア運用の第一歩は、明確な目的設定から始まります。目的が曖昧なまま運用を始めると、コンテンツの方向性が定まらず、結果として効果が分散してしまうことがあります。
運用体制は予算や人材リソースによって最適な体制を構築し、更新頻度はユーザーの期待とSEO効果のバランスを考慮して決定していきます。
品質管理は、SEO効果とユーザー満足度の両方に直結するため、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した品質管理体制を整えることが重要です。
オウンドメディアのSEO対策を成功に導く3つの柱

オウンドメディアのSEO対策を成功させるためには、バランスの取れた施策が必要です。特に重要となるのが「コンテンツSEO」「テクニカルSEO」「内部対策・外部対策」という3つの柱です。
これらの要素を適切に組み合わせることで、検索エンジンからの評価を高め、安定した流入を獲得できます。
コンテンツSEO
ユーザーが求める情報を、質の高いコンテンツとして提供することに重点を置きます。ユーザーに価値ある情報を届けることがGoogleの評価につながるため、以下で解説する3つの項目をSEO対策の中心的な要素として捉えましょう。
ユーザーファーストなコンテンツ作成
ユーザーファーストなコンテンツ作成は、オウンドメディアのSEO対策において重要な要素の一つです。Googleも「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」という方針を掲げており、ユーザーの役に立つコンテンツが結果的にSEO評価の向上につながることがわかります。
キーワード選定
オウンドメディアのSEO対策では、効果的なキーワード選定も重要です。適切なキーワードを選定することで、検索エンジンからの流入を最大化し、コンバージョンにつなげることが可能になります。キーワード選定の際は、以下の基準を参考にしてください。
| 基準 | 詳細 |
|---|---|
| 検索ボリューム | • 月間検索数1,000~10,000を目安とする • ロングテールキーワードも狙う • 季節変動や時期性を考慮する |
| 競合性 | • 上位表示サイトの競合度を分析 • 難易度と獲得可能性を評価 • 必要なリソースを見積もる |
| 関連性 | • 事業内容との親和性を確認 • 商材・サービスとの結びつき • 自社の強みを活かせるか判断 |
検索ボリュームは、そのキーワードが月間でどれくらい検索されているかを示す指標です。一般的には、月間検索数1,000~10,000程度のミドルキーワードを狙うのが効果的とされています。
競合性は、選定したキーワードで検索したときに表示される上位サイトの強さを評価する基準です。競合サイトのドメインパワーや被リンク状況、コンテンツの質などを分析し、自社が上位表示を獲得できる可能性を判断します。
関連性は、選定したキーワードが自社の事業内容や提供する商材・サービスとどれだけ関連しているかを評価する基準です。いくら検索ボリュームが多くても、自社のビジネスと関連性が低いキーワードで流入したユーザーは、コンバージョンにつながりにくいため、適切とはいえません。
E-E-A-T対策
E-E-A-Tは、Experience(経験・体験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の略称で、Googleの検索品質評価ガイドラインにおいて重要項目として位置づけられています。
オウンドメディアのSEO対策において、E-E-A-Tを高めることは検索順位向上に直結する重要な要素となります。
参考:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加
テクニカルSEO
テクニカルSEOは、オウンドメディアの検索順位を向上させるために欠かせない技術的な対策です。どれだけ質の高いコンテンツを作成しても、クローラーがサイトを適切に巡回できなかったり、コンテンツを正しく認識できなかったりすれば、その価値は十分に発揮されません。
テクニカルSEOは、Googleにサイトの価値を正しく伝えるための土台といえるでしょう。
サイト構造の最適化
オウンドメディアのSEO対策において、サイト構造の最適化は検索順位向上の重要な鍵となります。適切なサイト構造は、Googleのクローラーがコンテンツを効率的に巡回できるだけでなく、ユーザビリティも向上させるため、滞在時間の延長やコンバージョン率の改善にも貢献します。以下2つの要素について、最適化していきましょう。
| 要素 | 最適化ポイント |
|---|---|
| URL設計 | • シンプルで理解しやすい構造 • キーワードを含める • 短く簡潔な設計 |
| 階層構造 | • 適切な深さ(3階層程度) • 論理的なカテゴリ構成 • ユーザビリティを考慮 |
URL設計はSEOとユーザビリティの両面で重要な役割を果たします。最適なURLは、シンプルで理解しやすく、短く簡潔であるべきです。例えば、ブログ記事のタイトルが「SEOに強いオウンドメディアにするには?構築方法や運用時の注意点など徹底解説」という場合、URLには「owned-media-seo」のようにキーワードを含む短い文字列を使用するのが効果的です。
サイトの階層構造は、情報を整理して提示する上で重要な要素です。理想的な階層構造は、深さが3階層程度に収まっていて、ユーザーが目的のコンテンツに迷わずアクセスできるものです。具体的には「トップページ > カテゴリページ > 個別ページ」という流れで、どのコンテンツにも数クリック以内でたどり着ける設計が望ましいでしょう。
モバイルフレンドリー対応
モバイルフレンドリーとは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末で適切に表示・操作できるWebサイトの状態を指します。現代のオウンドメディア運営において、モバイルフレンドリー対応は必須の要素となっています。
検索トラフィックの過半数がモバイル端末からのアクセスです。
Googleはモバイルファーストインデックスという方針を採用しており、Webページのインデックスと順位付けにおいて、モバイル版のコンテンツを優先的に使用します。これは2019年7月から新規サイトに対して適用が開始され、現在ではほぼすべてのウェブサイトがこの方針の対象となっています。
表示速度の改善
Webページの表示速度の最適化も重要です。特に、モバイル端末は通常PCに比べて処理能力が低く、また通信環境も安定しないことがあるため、ページの読み込み速度がユーザー体験に大きく影響します。
Googleの調査によると、ページの読み込みが3秒を超えると53%のユーザーがそのサイトを離れてしまうという結果が出ています。
表示速度のチェックには、Googleが提供している「PageSpeed Insights」が有用です。URLを入力するだけで、モバイルとデスクトップそれぞれの表示速度スコアが表示され、改善すべき項目が具体的に提案されます。
内部対策
内部対策はオウンドメディアのSEO効果を高める上で不可欠な要素であり、ユーザビリティの向上とクローラビリティの改善を同時に行える施策です。
特に内部リンクの適切な構築とパンくずリストの効果的な活用は、コンテンツの価値を最大化する重要な対策となります。これらの内部施策を適切に実装することで、サイト全体の評価向上と検索順位の改善につながります。
内部リンクの構築
内部リンクとは、同じドメイン内のページ間をつなぐリンクのことです。適切に設置された内部リンクには、クローラーがページを見つけるきっかけになるほか、ページの重要性を示すヒントになる役割があります。
内部リンクの効果的な構築には、まず文脈に沿った自然なリンク設置が基本となります。記事中に関連するキーワードや用語が出てきた際に、そのテーマについて詳しく解説しているページへリンクすることで、ユーザーに価値ある情報を提供できます。
パンくずリストの活用
パンくずリストは、ユーザーがサイト内のどこにいるかを示す階層順のナビゲーションで、「トップページ > カテゴリ > サブカテゴリ > 現在のページ」といった形式で表示されます。名称は「ヘンゼルとグレーテル」の童話で、道に迷わないように落としていったパンくずに由来しています。
パンくずリストの主な役割はユーザビリティの向上です。ユーザーは現在の位置を常に把握でき、上位階層に簡単に戻ることができるため、サイト内で迷子になりにくくなります。
また、パンくずリストは内部リンクの一種でもあるため、クローラーのサイト巡回を助ける効果もあります。
外部対策
オウンドメディアのSEO対策において、外部対策は内部対策と並ぶ重要な柱です。外部対策とは、自社サイト以外の場所から評価を得ることでサイトの権威性を高め、検索エンジンからの評価を向上させる施策を指します。
特にGoogleのアルゴリズムでは、他サイトからの評価が重要な順位決定要因となっているため、計画的な外部対策が不可欠です。
被リンクの獲得
外部対策の中核となるのが被リンクの獲得です。被リンクとは他のウェブサイトから自社サイトへのリンクのことで、Googleはこれを「他者からの推薦票」と見なします。
ただし、単に数を増やせばよいわけではなく、リンク元サイトの質や関連性が極めて重要となります。
| 獲得方法 | 具体的なアプローチ |
|---|---|
| コンテンツ制作 | • データや統計を用いたオリジナルコンテンツ • 業界の最新トレンド分析 • 専門家による詳細な解説記事 • ユーザー調査のレポート化 |
| PR活動 | • プレスリリースの定期的な配信 • ニュースサイトへの掲載 • メディアへの独占情報提供 • 業界ポータルサイトへの情報提供 |
| 外部連携 | • 業界インフルエンサーとの共同コンテンツ制作 • パートナー企業との共同調査 • 専門家へのインタビュー記事 • 業界団体との協力関係構築 |
高品質なコンテンツ制作は、自然な被リンクを生み出す最も効果的な方法です。オリジナリティの高い価値あるコンテンツを制作することで、他サイトから参照されやすくなります。データや統計を用いたオリジナルコンテンツは特に効果的です。独自調査や分析結果を公開することで、その情報を引用したい他メディアから自然とリンクを獲得できます。
積極的なPR活動も被リンク獲得手段の一つです。自社の活動や成果を効果的に外部に発信することで、メディアからの注目を集めることが可能になります。なかでもプレスリリースの定期的な配信は、基本的かつ効果的な手法と言えます。
他組織との連携も質の高い被リンクを獲得する有効な方法です。異なる視点や専門性を組み合わせることで、より価値の高いコンテンツを生み出せる可能性があります。
プレスリリース・SNS活用
プレスリリースとSNSの活用は、オウンドメディアのSEO効果を高める強力な外部対策となります。これらのチャネルを戦略的に活用することで、被リンクの獲得や認知度向上、さらにはブランド価値の強化まで行える可能性があります。
SNSは直接的なSEOランキング要因ではないものの、コンテンツの拡散やブランド認知、そして間接的な被リンク獲得に貢献します。
最も効果的なのは、プレスリリースとSNSを連動させる戦略です。プレスリリース配信後にSNSでも同内容を拡散し、さらに社内メンバーによる個人アカウントでのシェアも促進することで、リーチを最大化します。さらに、SNSでの反応やエンゲージメント分析を通じて、コンテンツ戦略の改善にも役立てることができるでしょう。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
オウンドメディアでSEO対策を行う手順

オウンドメディアのSEO対策は、ただ闇雲に記事を投稿するだけでは効果を得られません。戦略的な計画と段階的な実行がポイントです。以降では、以下3つのステップでSEO対策の手順を解説していきます。
- 施策立案と目標設定
- コンテンツ制作の体制構築
- 効果測定と改善サイクルの確立
①施策立案と目標設定
オウンドメディアのSEO対策を成功させるためには、効果的な施策計画の立案と適切なKPI設定が不可欠です。明確な目標を設定することで、施策の優先順位が付けやすくなり、効果測定も正確に行えるようになります。目標設定には、以下のような項目を検討しましょう。
| 項目 | 具体的な指標 |
|---|---|
| トラフィック | • PV(ページビュー)数 • UU(ユニークユーザー)数 • オーガニック流入数 • 新規訪問者数 |
| エンゲージメント | • 直帰率 • 平均滞在時間 • ページ/セッション • リピート率 |
| コンバージョン | • CVR(コンバージョン率) • 問い合わせ数 • 資料請求数 • メルマガ登録数 |
トラフィックは、サイトへの訪問者数や閲覧数を表す指標です。SEO施策の初期段階では特に重要な測定対象となります。
例えば、現在月間オーガニック流入が5,000セッションの場合、6ヶ月後に10,000セッション(2倍)を目指すといった具体的な数値目標を設定します。この際、過去のトレンドや業界平均、競合状況なども考慮して現実的な目標値を設定することが大切です。
また、単純な総量だけでなく、狙ったキーワードからの流入増加や、特定のターゲットページへの流入増加など、質的な側面も含めたKPI設定が効果的です。
②コンテンツ制作の体制構築
施策の立案と目標設定が完了したら、次は継続的に質の高いコンテンツを発信できる体制を構築します。単発的な記事投稿ではなく、長期的視点での運営が重要となるため、効率的な制作フローの確立が成功への近道となります。
効率的なコンテンツ制作体制を構築するためには、まずコンテンツ戦略の明確化から始めましょう。ターゲットユーザーのペルソナ設定、解決すべき課題の特定、競合調査などを通じて、どのようなコンテンツが必要かを具体化することが第一歩です。
次に、コンテンツ制作に必要なリソースを洗い出します。一般的なコンテンツ制作には、企画立案者、ライター、編集者、SEO担当者、デザイナー、ウェブ担当者などの人材が関わります。これらすべてを社内で確保することが理想的ですが、現実的には難しいこともあるでしょう。そのため、自社の強みと弱みを把握し、どの部分を内製化し、どの部分を外部委託するか判断します。
効率的な制作サイクルを回すためには、ワークフロー管理ツールの導入も検討しましょう。
③効果測定と改善サイクルの確立
コンテンツは投稿して終わりではありません。効果測定と改善のサイクルを確立することが不可欠です。
単に良質なコンテンツを発信するだけでなく、その効果を正確に把握し、データに基づいた改善を重ねることで、長期的な成果につながります。以下の計測、評価、改善のステップを繰り返し、ユーザーファーストなオウンドメディアに育てていきましょう。
| ステップ | 実施内容 |
|---|---|
| 計測 | • アクセス解析データの収集 • ユーザー行動の分析 • 検索順位の追跡 • コンバージョンデータの収集 |
| 評価 | • KPIの達成度確認 • ユーザー導線の分析 • 問題点の特定 • 改善機会の発見 |
| 改善 | • コンテンツの最適化 • UI/UXの改善 • 技術的対策の実施 • 新規コンテンツの追加 |
計測のステップでは、さまざまなデータを収集することから始まります。アクセス解析ツールを活用して、ページビュー数、セッション数、ユーザー数などの基本的な指標を把握することが基本となります。
Google Analyticsなどのツールを利用すれば、訪問者の流入経路、滞在時間、直帰率などの詳細なデータを収集することが可能となります。特に重要なのは、検索エンジンからの流入が増えているか、またどのキーワードで流入しているかを把握することです。
評価のステップでは、収集したデータを分析し、成果と課題を明確にします。まず、設定したKPIの達成度を確認することから始めましょう。月間PV数、新規ユーザー数、コンバージョン率など、事前に定めた指標に対しての達成状況を評価します。単純な数値の増減だけでなく、トレンドや季節変動なども考慮して多角的に分析することが大切です。
ユーザー導線の分析も評価の重要な要素となります。ユーザーがサイトにアクセスしてから離脱するまでの経路を追跡し、どのページでつまずきが発生しているかを特定します。例えば、特定のページからの離脱率が高い場合、そのページのコンテンツや導線に問題がある可能性があり、改善の余地が見つかるでしょう。
改善のステップでは、評価で得られた知見をもとに具体的なアクションを実行します。コンテンツの最適化は最も基本的な改善施策となります。既存コンテンツの見直しを行い、キーワードの適切な配置、メタディスクリプションの改善、見出し構造の最適化などを実施することで、検索エンジンからの評価向上を図りましょう。
まとめ
オウンドメディアのSEO対策は、一時的なテクニックではなく、ユーザーと検索エンジンの双方に価値を提供し続ける長期的な取り組みです。コンテンツSEO、テクニカルSEO、内部・外部対策の3つの柱をバランスよく強化し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことがポイントとなります。
明確な目標設定、効率的な制作体制、そして効果測定の仕組みを構築し、自社の成長につながるメディアを運用していきましょう。













