
Webコンテンツの作成にWebライティングは欠かせないスキルとなっています。検索エンジンからの流入を増やしながら、読者に価値ある情報を届けるこの技術は、デジタルマーケティングにおいて重要となっています。
本記事では、Webライティングの基礎知識から実践テクニック、避けるべき間違い、SEO対策、スキルアップ方法まで体系的に解説します。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
Webライティングとは?

Webライティングとは、インターネット上のユーザーに向けてコンテンツを提供するために文章を書くことです。ブログ記事やWebサイトのテキスト、メールマガジンなど、オンライン上で読まれることを前提とした文章作成全般を指します。
紙媒体の文章と異なり、Webライティングは画面上で読まれることを考慮したスキルが求められます。
Webライティングの目的
Webライティングの主な目的は、ユーザーが求める情報や解決策を分かりやすく提供することです。インターネット上には膨大な情報が存在しており、ユーザーはその中から自分に必要な情報をすばやく見つけ出そうとしています。
そのため、Webライティングでは「結論ファースト」の構成を取り入れたり、見出しを適切に配置したりすることで、読者が欲しい情報に素早くたどり着けるよう工夫する必要があります。
通常のライティングとWebライティングの違い
紙媒体のライティングとWebライティングには、いくつかの明確な違いがあります。最も大きな違いは、情報の消費スピードです。
雑誌や書籍などの紙媒体は、じっくりと読むことを前提としていますが、Webコンテンツは多くの場合、読者が必要な情報をすぐに見つけ出すことを求めています。
| 比較項目 | 通常のライティング | Webライティング |
|---|---|---|
| 媒体 | 紙媒体(書籍・雑誌など) | Webサイト・ブログなど |
| 情報量 | ページ数制限あり | 制限なし |
| 読まれ方 | じっくり読まれる | 飛ばし読み・立ち読み的 |
| レイアウト | 固定 | デバイスにより変化 |
| 検索性 | なし | 検索エンジンから流入 |
Webライティングに必要な技術
効果的なWebライティングを行うためには、いくつかの重要な技術を習得する必要があります。まず、「SDS法」や「PREP法」といった文章構成のテクニックを理解しておくことが重要です。
SDS法は「要約(Summary)→詳細(Detail)→要約(Summary)」の順に情報を提示する方法で、PREP法は「結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)」という流れで説明する手法です。これらの型を活用することで、読者に分かりやすい文章を作ることができます。
SEOの基礎知識も不可欠です。適切なキーワード選定や配置、内部リンクの活用などがこれにあたります。ただし、SEOを意識するあまり文章の読みやすさを損なわないよう注意が必要です。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
Webライティングの書き方・始め方

効果的なWebコンテンツを作成するには、単に文章を書くだけでなく、計画的なプロセスに従って進めることが重要です。ここでは、リサーチから編集・校正までの一連の流れを詳しく解説します。
リサーチをする
質の高いWebコンテンツを作成するためには、まず徹底的なリサーチが欠かせません。的確な情報収集が、魅力的で価値のある記事の土台となるからです。
信頼性の高いWebサイト、書籍、学術論文などから情報を集め、テーマに関する理解を深めましょう。このとき、単一の情報源だけでなく、複数の情報源を参照することで、より客観的かつ包括的な視点を得ることができます。
構成を作る
リサーチが完了したら、次は記事の構成を考える段階に移ります。しっかりとした構成があることで、論理的に整理された分かりやすい文章になり、読者の理解を助けることができます。
タイトル、見出し、各セクションの概要などを記載し、記事全体の流れを可視化します。構成を作成する際は、読者がどのような順序で情報を得ると理解しやすいかを考慮しましょう。
執筆する
構成が決まったら、いよいよ実際の執筆作業に入ります。Webライティングでは、読みやすさと伝わりやすさを最優先に考えながら文章を組み立てていきましょう。
執筆を始める前に、静かな環境を整え、集中できる状態を作ることが大切です。スマートフォンの通知をオフにしたり、BGMを流したりと、自分が最も集中できる環境を整えましょう。また、一度に長時間書くよりも、適度な休憩を挟みながら執筆する方が、質の高い文章を維持しやすくなります。
編集・校正
執筆が完了したら、次は編集・校正の段階に入ります。この工程は、記事の品質を高め、信頼性を高めるための重要なステップです。
リリース前の最終チェックとしては、タイトルと見出しが内容を反映しているか、文法や表記の統一性が保たれているか、誤字脱字がないか、画像や図表が適切に配置されているか、引用や参考文献が正しく記載されているかを確認します。
読者に伝わるWebライティングのコツ
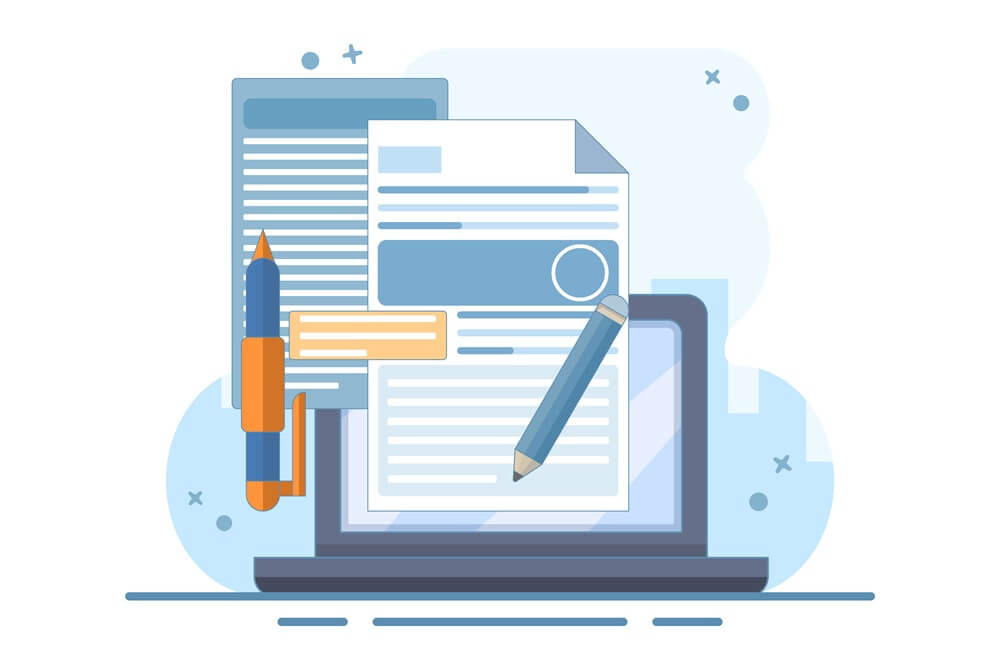
効果的なWebライティングを行うためには、単に情報を伝えるだけでなく、読者の心をつかむための工夫が必要です。ここでは、Webライティングの質を高めるための具体的なコツをご紹介します。
結論ファーストを徹底する
Webコンテンツにおいて、「結論ファースト」は最も重要な原則の一つです。これは、文章の冒頭で主要なポイントや結論を述べ、その後に詳細や根拠を展開していく方法です。
インターネット上のユーザーは、情報をすばやく得たいという特性があります。全ての文章を最初から最後まで読むわけではなく、多くの場合、冒頭部分だけを読んで、そこに求める情報がなければ別のページに移ってしまいます。そのため、最初に重要なポイントを示すことが欠かせません。
わかりやすい表現
Webライティングでは、読者にとってわかりやすい表現を用いることが非常に重要です。難解な専門用語や複雑な言い回しは避け、平易な言葉で説明しましょう。
専門用語を避けることの重要性は、特に一般向けのコンテンツでは無視できません。専門家にとっては当たり前の用語でも、一般の読者にとっては理解の妨げになることがあります。もし専門用語を使用する必要がある場合は、簡単な説明を加えると良いでしょう。
たとえば「SEO(検索エンジン最適化)とは、GoogleなどのWeb検索で上位表示されるようにWebサイトを最適化することです」というように、括弧内や文中で解説を加えることで理解を助けます。
数値化した説明
Webライティングにおいて、抽象的な表現を具体的な数値に置き換えることは、文章の説得力と信頼性を高める重要な要素です。数値を用いることで、読者に明確なイメージを与え、情報の価値を高めることができます。
形容詞を数値に変換すると、曖昧さを排除し具体性を増す効果があります。たとえば、「多くの人が利用している」という表現は、「約70%のユーザーが利用している」という数値表現に置き換えることで、より説得力が増します。同様に、「短時間で」という表現よりも「約15分で」、「頻繁に」よりも「週に3回」というように具体的な数値を示すことで、読者は明確なイメージを持つことができます。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
SEOを意識したWebライティングのコツ

Webライティングでは単に読みやすい文章を書くだけでなく、検索エンジンからの評価も意識する必要があります。検索エンジン最適化(SEO)に配慮した文章は、より多くの読者に届き、コンテンツの価値を最大化します。
ここでは、SEOに強い記事を書くための具体的なテクニックをご紹介します。
ユーザーニーズを満たす情報
SEOにおいて最も重要なのは、ユーザーが求める情報を的確に提供することです。検索エンジンのアルゴリズムは年々高度化し、ユーザーにとって価値ある情報を提供しているかを見極める精度が向上しています。
ユーザーの検索意図を把握するための有効な方法として、Googleの検索結果ページを分析する手法があります。特定のキーワードで検索したときに上位表示されるコンテンツの特徴(記事の長さ、見出し構成、含まれる情報など)を調査することで、そのキーワードでユーザーが求めている情報の傾向がわかります。
キーワードの適切な配置
SEOを意識したWebライティングでは、キーワードの配置が重要なポイントとなります。ただし、キーワードを単に詰め込むのではなく、自然な形で適切に配置することが求められます。自然な形でのキーワード配置は、読者の読みやすさを保ちながらSEO効果を得るための基本です。
キーワードを自然に配置するためのポイントとして、まずはタイトルと見出しへの含有が挙げられます。特にH1タグ(記事タイトル)には必ず主要キーワードを含めるようにしましょう。H2、H3などの見出しには、主要キーワードやその派生語、関連キーワードを適宜配置します。
本文中でのキーワード配置も重要です。特に記事の冒頭部分(リード文)や最初の段落には、主要キーワードを含めるようにしましょう。
Webライティングで避けるべきこと

効果的なWebライティングを実現するためには、良い文章の書き方を知るだけでなく、避けるべき点も理解することが重要です。ここでは、Webライティングで陥りがちな典型的な間違いとその対処法について説明します。
冗長な表現はWebライティングにおいて大きな障害となります。特に「この記事では〜について解説します」「〜について説明しましょう」などの余計な前置きは、情報の密度を下げるだけでなく、読者の時間も奪ってしまいます。このような表現は削除し、すぐに本題に入ることで読者の関心を維持しやすくなります。
説明不足
Webライティングにおいて説明不足は、読者の理解を妨げる大きな要因となります。特に専門的なトピックを扱う場合、書き手は既に基本知識を持っているため、当たり前と思って説明を省略してしまうことがあります。
読み手の知識レベルを適切に想定することが重要です。ターゲット読者が専門家なのか初心者なのかによって、説明の詳細さは大きく変わります。
初心者向けのコンテンツであれば、専門用語の解説や基本的な概念の説明を丁寧に行う必要があります。一方、専門家向けであれば、基礎的な説明は省略し、より深い知見や最新情報を提供することが求められます。
不適切表現
Webライティングにおける不適切表現は、読者の不快感を招くだけでなく、記事やサイト全体の信頼性を損なう可能性があります。特に公開されるコンテンツでは、多様な背景を持つ読者に配慮した表現を心がけることが重要です。
差別語や不快語の使用は絶対に避けるべきです。歴史的背景や文化的文脈によって差別的とされる言葉は、たとえ悪意がなくても読者を傷つける可能性があります。差別語の代替表現として、より中立的で客観的な表現を選ぶようにしましょう。
たとえば、特定の国や地域、民族を揶揄するような表現は使わず、正式名称を用いることが基本です。
コンプライアンス違反
Webライティングにおけるコンプライアンス違反は、単に倫理的な問題だけでなく、法的責任を問われる可能性もある重大な問題です。特に注意すべきは著作権侵害で、他のWebサイトや書籍からの無断転載は厳に慎むべきです。
著作権侵害の具体例としては、他サイトの記事をそのままコピーする、画像を無断使用する、他者の文章を一部変更しただけで自分の文章として公開するなどが挙げられます。これらの行為は著作権法違反となり、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
Webライティング後の校正のポイント

Webライティングで質の高いコンテンツを作成するためには、執筆後の校正作業が非常に重要です。丁寧な校正によって、文章が読みやすくなり、ユーザーが記事を最後まで読んでくれるようになります。
ここでは、記事の品質を高めるための校正のポイントと具体的な方法について説明します。
誤字脱字の修正
誤字脱字は、コンテンツの信頼性や読者の印象に大きな影響を与えます。一字の誤りであっても、読者はその記事の信頼性に疑問を持ちかねません。
特にWebコンテンツは紙媒体と異なり、公開後でも修正が容易なため、「後で直せばいい」という姿勢ではなく、公開前に徹底的にチェックする習慣を身につけることが大切です。
固有名詞のチェック
固有名詞の誤りは、記事の信頼性に直結する問題です。特に企業名、人名、商品名などが間違っていると、専門知識の不足と見なされ、記事全体の価値が損なわれる可能性があります。
人名・企業名・商品名の確認は、非常に重要なチェックポイントとなります。たとえば、人名では「鈴木」と「鈴城」、企業名では「サニー」と「ソニー」のように、一文字違いでも全く異なる意味になってしまいます。こうした固有名詞は、記事内で初めて登場する際に特に注意深くチェックする必要があります。
表記の統一
表記の統一は、プロフェッショナルな印象を与えるWebコンテンツにとって非常に重要です。同じ言葉に対して複数の表記方法が混在していると、読者に違和感を与え、コンテンツの質が低いという印象を持たれかねません。
表記を統一するためには、あらかじめスタイルガイドを作成しておくことが効果的です。特に頻繁に使用する用語や、表記揺れが起こりやすい言葉については、どの表記を採用するか事前に決めておきましょう。
たとえば「Web」と「ウェブ」、「インターネット」と「ネット」、「検索エンジン最適化」と「SEO」など、複数の表現が可能な言葉は特に注意が必要です。
Webライティングを習得するための学習方法

Webライティングのスキルを磨くには、体系的な学習と継続的な実践が欠かせません。ここでは、効果的にWebライティングを習得するための学習方法をご紹介します。
セミナーに参加する
Webライティングのセミナーは、短期間で集中的に知識やスキルを習得できる機会です。対面やオンラインで開催されるセミナーには、業界の最新トレンドや実践的なテクニックを学べるという大きなメリットがあります。
講座を受講する
Webライティング講座は、セミナーよりも長期間にわたって体系的に学べる場です。基礎から応用まで段階的にスキルを積み上げていけるため、特に初心者の方にはおすすめの学習方法です。
講座には、さまざまな種類があります。オンラインで自分のペースで学べるものから、対面式で講師やクラスメイトとの交流を重視するもの、実務に直結した実践型のものまで、目的やライフスタイルに合わせて選べます。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
Webライティング用ツールの活用

効率的で質の高いWebライティングを実現するためには、適切なツールの活用が欠かせません。現在ではさまざまなWebライティング支援ツールが開発されており、これらを上手に使いこなすことで執筆作業の効率化や品質向上が期待できます。
| ツールカテゴリ | 代表的なツール | 主な機能 |
|---|---|---|
| SEO分析ツール | Ahrefs | キーワード分析 |
| 記事作成支援ツール | tami-co | キーワード分析、構成案作成 |
| 文章校正ツール | Googleドキュメント、Microsoft Word | スペルチェック、文法チェック |
SEO分析ツールとして代表的なのは、Ahrefsが挙げられます。Ahrefsは、キーワードリサーチ、競合分析、バックリンク分析など、SEOに関する幅広い機能を提供しています。特にキーワード分析機能は、特定のキーワードの検索ボリュームや難易度、関連キーワードなどを詳細に調査できるため、記事テーマの選定や構成検討に役立ちます。
記事作成支援ツールは、コンテンツの企画から執筆、編集までの一連のプロセスをサポートするツールです。tami-coはキーワード分析から構成案作成まで、Webライティングのフローを一括で行える機能を備えています。
文章校正ツールは、誤字脱字のチェックや文法ミスの指摘、表現の統一性確認など、文章の品質を向上させるために欠かせないツールです。品質の高い文章は読者の信頼を獲得し、コンテンツの価値を高めます。
多くの人が日常的に使用しているGoogleドキュメントやMicrosoft Wordにも、基本的な文章校正機能が搭載されています。スペルチェックや文法チェック、読みやすさの分析など、文章の基本的な品質を確保するための機能が利用できます。
まとめ
Webライティングは、オンライン上で読者に価値を届けるための重要なスキルです。検索エンジンからの流入を意識した構成や、読者にストレスなく伝わる表現技術を身につけることで、効果的なコンテンツ作成が可能になります。
適切なリサーチから始まり、読者目線の構成、わかりやすい執筆、丁寧な校正までの一連のプロセスを習得することが成功への鍵となります。Webライティングのスキルを磨くことで、ビジネスの成長やブランド構築に貢献し、オンラインでの存在感を高めることができるでしょう。













