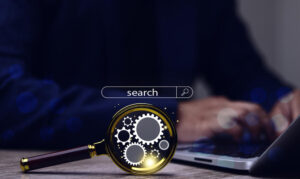SEO対策を行うにあたって、検索順位の突然の低下は多くのWebサイト運営者を悩ませる深刻な課題です。長年にわたって築き上げてきた検索結果の上位を維持することは、デジタルマーケティングにおいて極めて重要な戦略的目標となっています。
検索順位が急落した際に、冷静に原因を特定し、適切な対策を講じることが、トラフィックの回復とサイト成長のポイントとなるのです。本記事では、検索順位が下がってしまう理由や、具体的な改善方法などを解説していきます。
検索順位が急に落ちてしまった時に考えられる理由

検索結果の上位にあった記事が急に下落すると、検索エンジンからの流入を確保して売上を担保している企業や個人にとっては甚大な影響を被ることになります。
順位が下がってしまったとき、焦って対策を講じるのではなく、まずは冷静に原因を分析し、適切な対応策を考えることが、検索順位回復への近道となります。
自サイトに改善点がある場合
自サイトに問題がある場合、検索順位が下がる可能性は非常に高くなります。ここでは、自サイトに起因する主な原因について解説します。
【コンテンツの質が低下している】
記事公開当初は過大評価されていたものの、時間の経過とともに記事の質の低さが露呈し、検索順位を落としているケースがあります。Googleは情報が誤っている、内容が薄い、専門家によって書かれていないといった要素を低品質と判断します。
特に複数のライターを抱える企業メディアでは、記事の質にばらつきが生じやすいため、執筆レギュレーションの整備が重要です。また、長期間情報を更新していないことも順位下落の原因になります。
【テクニカルSEOに問題がある】
noindex設定の誤り、robots.txtの誤設定、サーバーエラーの発生、内部リンク構造の変更など、技術的な問題も検索順位低下の大きな要因となります。特にページに誤ってnoindexタグが設定されていると、検索結果に表示されなくなるため注意が必要です。
【過剰なSEO対策を実施している】
キーワードの濫用、不自然なリンク構築、重複コンテンツの大量投稿などの過剰なSEO対策も順位下落の原因となります。これらは一時的に効果があっても、長期的にはGoogleのガイドラインに反し、ペナルティを受ける可能性があります。
競合サイトに要因がある場合
SEOは相対評価で決まるため、自社サイトに問題がなくても競合サイトの状況によって検索順位が下落することがあります。検索エンジンは常に最適な検索結果を提供するため、より質の高いコンテンツを上位表示させる仕組みを持っています。
競合サイトが強い評価を受けている場合、通常は網羅的なコンテンツ、独自性の担保、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の高さといった特徴があります。これらの要素によって競合サイトの評価が上がれば、自社サイトが順位を落とすことになります。
競合分析には、Ahrefsなどのツールを活用して被リンク数やドメインランクを確認し、どのような点で競合が優位に立っているかを特定することが重要です。この分析をもとに自社サイトの改善方針を決定しましょう。
Googleアルゴリズムアップデートの場合
検索順位の低下には、Googleのアルゴリズム変更が大きな影響を及ぼしていることがあります。アルゴリズム更新には、年に数回実施される「コアアルゴリズムアップデート」と、ほぼ毎日行われる「日々の小さなアップデート」があります。
影響範囲を特定するには、Googleサーチコンソールのパフォーマンスレポートでアップデート前後のデータを比較し、サイト全体か特定ページだけが影響を受けているかを分析しましょう。コアアップデートの場合は、すぐに改善するのではなく、まずは状況把握と揺り戻しの可能性を考慮して静観することが重要です。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
検索順位下降の要因を特定するためのチェック項目

順位下落の原因究明は早急に取り組むべき課題と言えるでしょう。このような時には、要因を特定するためのチェック項目を系統的に確認していくことが重要です。
Googleの公式アナウンスを確認するところから始め、自社サイトの問題、そして競合サイトとの比較へと調査を進めていきましょう。
Goolgle公式アナウンスで発表されていることはないか
検索順位が低下した場合、まず最初に確認すべきは、Googleが公式に発表しているアルゴリズムの変更情報です。Googleは定期的に検索アルゴリズムを更新しており、その変更内容がサイトの評価に影響を与えることがあります。
Googleのアルゴリズム変更情報は、以下の公式チャンネルで確認することができます。
これらの情報源を定期的にチェックすることで、検索順位の変動が大規模なアルゴリズム変更によるものかどうかを判断できます。たとえば、「コンテンツの質」や「ページエクスペリエンス」を重視するアルゴリズム変更が発表されている場合、それらの指標が自社サイトで低下していると検索順位も下がる可能性があります。
ブログのリライトなどを行っているか
検索順位低下の要因として、コンテンツのリライトや更新が影響していることがあります。質の低いコンテンツはGoogleから適切に評価されず、時間の経過とともに情報の誤り、内容の薄さ、専門知識の不足などが露呈すると評価が下がることがあります。
リライト時に重要な情報を削除したり、ユーザーの検索意図に沿わない情報を追加したり、特に流入数の多いクエリが含まれていた見出しを削除したりすることも順位下落の原因になります。
Googleサーチコンソールでクリック数や表示回数を事前に確認し、重要な見出しの変更は慎重に行いましょう。効果的なリライトは、情報を更新しつつも検索ユーザーの意図を理解し、それに応える内容を維持・拡充することがポイントです。
過剰なSEO対策を実施していないか
検索エンジンの上位表示を狙うあまり、過剰なSEO対策を施してしまうことで、かえって順位を下げてしまう可能性があります。Googleは不自然なSEO最適化を好ましくないと判断し、ペナルティを与えることがあるためです。
よくある対策としては、キーワードの濫用、被リンクを一気に増やすリンク構築、重複コンテンツの大量投稿などが挙げられます。見出しや本文内に対象キーワードを不自然なほど詰め込むと、スパムとして認識され、検索順位の低下を招きます。
過剰なSEO対策を行っていないか確認するには、Googleサーチコンソールでペナルティの有無をチェックし、不自然な最適化を避けることが重要です。
SSL化を行っていたか
常時SSL化(HTTPS化)やサイトリニューアルを行った場合、適切に設定ができていないと検索順位が下がることがあります。SSL化は現在のWeb標準であり、セキュリティ面で重要ですが、移行時には混合コンテンツの発生など注意が必要です。
特に注意すべきは、サイトリニューアルでドメインやURLを変更した場合です。これまで積み上げてきたGoogleからの評価がゼロになってしまうリスクがあります。このような事態を防ぐためには、301リダイレクトなどの適切なリダイレクト設定が不可欠です。
リダイレクト設定により、旧URLから新URLへの恒久的な転送を指示し、これまでの評価を新URLに引き継ぐことができます。適切な移行作業を行わないと、検索順位に大きな影響を与える可能性があるため注意しましょう。
ページがnoindexになっていないか
突然検索順位が下がった場合、ページにnoindexタグが誤って設定されていないか確認することが重要です。noindexとは、検索エンジンに「このページをインデックスしないでください」と指示するメタタグであり、設定されているページは検索結果に表示されなくなります。
noindexタグの確認方法としては、Google Chrome開発者ツールを使用してページのソースを表示し、「noindex」というキーワードを検索する方法があります。WordPressでは、SEO関連プラグインの設定画面で確認できることが多いでしょう。
robots.txtでクローラーを弾いていないか
robots.txtファイルは、検索エンジンのクローラーに対してサイト内のどのページやディレクトリをクロールしてよいか指示するためのファイルです。設定ミスにより、重要なページが検索エンジンにクロールされず、検索結果から除外されてしまうことがあります。
クロールを弾いてしまう主な原因としては、開発環境での設定が本番環境にそのまま適用されている場合や、設定の記述ミスなどが考えられます。robots.txtの確認は、ブラウザで「サイトのURL/robots.txt」と入力することで簡単に行えます。
適切なrobots.txt設定により、クロールの効率化と不要なページのクロール防止ができますが、誤った設定は検索順位に悪影響を及ぼすため、定期的な確認が大切です。
ページエクスペリエンスが低下していないか
Webサイトの検索順位低下に悩む運営者にとって、ページエクスペリエンスは極めて重要な評価指標となっています。Googleは、ユーザーに最適な閲覧体験を提供するサイトを高く評価するため、これらの指標を徹底的に分析しています。
主要なページエクスペリエンス指標と目標値は以下の表の通りです。各数値は、PageSpeedInsightを利用することで、確認可能です。
| 指標 | 概要 | 良好とされる目標値 |
|---|---|---|
| LCP(最大コンテンツ描画時間) | ページの読み込み開始から、最大の要素が表示されるまでの時間 | 2.5秒以下 |
| FID(入力の遅延時間) | ユーザーの操作からブラウザの応答までの時間 | 100ミリ秒以下 |
| CLS(視覚的安定性) | ページ読み込み中の要素の予期せぬ移動 | 0.1以下 |
これらの指標は、モバイルフレンドリー性、HTTPS、セキュリティ、インタースティシャル広告の影響と組み合わせて、総合的なページエクスペリエンスを評価します。ユーザーの快適な閲覧体験を追求することが、検索順位維持のポイントとなるのです。
重複コンテンツとみなされていないか
検索順位低下の重大な要因として、重複コンテンツの存在が挙げられます。Googleは独自性のないコンテンツを厳しく評価し、サイトの信頼性に深刻な影響を与える可能性があります。
重複コンテンツには、同一サイト内で類似したコンテンツが存在する「内部重複」と、他のWebサイトから無断でコンテンツをコピーした「外部重複(コピーコンテンツ)」があります。このような重複は、検索エンジンからサイトの評価を分散させ、最悪の場合インデックスから除外されるリスクがあります。
独自性の高いコンテンツ作成と適切な対策が、検索順位を維持・向上させる重要な鍵となるのです。
モバイルフレンドリーに対応しているか
Googleは、モバイル端末からのユーザー体験を非常に重視し、モバイルファーストインデックスを導入しました。これは、モバイル版のコンテンツを主に評価して検索順位を決定することを意味しており、モバイルフレンドリー対応は今や選択肢ではなく、必須条件となっています。
モバイルフレンドリーとは、スマートフォンやタブレットからのアクセスに最適化されたWebサイトの特性を指します。レスポンシブデザイン、読みやすいテキストサイズ、タップしやすいボタン、適切な画像サイズなどが重要な要素となります。
ペナルティを受けていないか
検索順位が急落した場合、Googleからのペナルティが原因である可能性があります。ペナルティには主に二種類の形態があり、それぞれ異なる特徴と対処方法が存在します。
手動対策は、Googleの担当者が直接サイトを審査し、明確な違反を発見した際に適用されます。このタイプのペナルティは、Googleサーチコンソールを通じて具体的な警告が送付されるため、比較的対応しやすい特徴があります。一方、自動対策は、Googleのアルゴリズムによって機械的に判定され、特別な通知なく検索順位を大幅に下げる可能性があります。
サイト運営者にとって最も重要なのは、これらのペナルティを未然に防ぐことと、万が一ペナルティを受けた場合に迅速かつ適切に対応することです。常に最新のGoogleガイドラインを確認し、質の高いコンテンツ提供に注力することが、ペナルティリスクを最小限に抑える最良の方法となります。
検索順位が下がってしまった場合の改善ポイント

コンテンツマーケティングを行う上で、検索順位の変動は常に起こりうる現象です。しかし、適切なアプローチで順位を回復することは可能です。コンテンツの質を徹底的に見直し、根本改善を行うことが鍵となるでしょう。
ブログなど記事コンテンツのリライトを行う
検索順位を回復させるための最も効果的な方法の一つは、既存コンテンツの徹底的なリライトです。Googleが高く評価するコンテンツには、正確で信頼性の高い情報、ユーザーの課題を解決する実用的な内容、読みやすい構成が求められます。
リライトの際は、現在の検索意図を再確認し、最新のトレンドや情報を反映させることが重要です。専門性を高め、読者にとって真の価値を提供するコンテンツづくりが、検索順位回復への近道となるのです。
分析ツールを元にテクニカルSEOの改善を行う
検索順位の低下に悩むWebサイト運営者にとって、テクニカルSEOの徹底的な分析と改善は極めて重要な戦略となります。Googleサーチコンソールtなどの分析ツールを活用することで、サイトの技術的な問題点を正確に特定できます。
| 対策項目 | 内容 | 優先度 |
|---|---|---|
| XMLサイトマップ | クローラーに効率的にサイト構造を伝える | 高 |
| 内部リンク最適化 | 重要ページへの適切なリンク設定 | 高 |
| 構造化データ | コンテンツの意味をGoogleに伝える | 中 |
| ページ表示速度 | ユーザー体験と評価向上のための高速化 | 高 |
| モバイル対応 | スマートフォンでの閲覧体験の最適化 | 高 |
テクニカルSEO対策の核心は、検索エンジンにとって理解しやすいサイト構造を作ることです。XMLサイトマップは、クローラーがサイトの構造を効率的に把握するための重要な手段となります。内部リンクの最適化は、重要なページへの適切な誘導を可能にし、サイト全体の回遊性を高めます。
構造化データの実装は、Googleにコンテンツの意味をより正確に伝える効果があります。また、ページ表示速度の最適化は、ユーザー体験を大幅に向上させ、検索順位にポジティブな影響を与えます。
モバイル対応は現代のデジタル環境において特に重要で、スマートフォンでの閲覧体験を最適化することが求められています。
競合サイトを分析し、差別化を行う
検索順位を維持・向上させるために競合サイトとの徹底的な比較分析は不可欠となっています。単に競合をコピーするのではなく、独自の強みを見出し、戦略的に差別化を図ることが必要です。
| 比較ポイント | チェック内容 | 改善アプローチ |
|---|---|---|
| 情報の正確性・網羅性 | 公式情報との相違がないか、必要な情報を網羅しているか | 情報の更新、コンテンツの拡充 |
| 専門性・権威性 | 専門家による執筆・監修、業界での認知度 | 専門家の起用、監修体制の強化 |
| 被リンク状況 | 被リンク数、リンク元の質、獲得頻度 | 質の高いコンテンツ提供、外部露出の増加 |
| ユーザー体験 | 読みやすさ、操作性、表示速度 | UI/UX改善、ページ速度最適化 |
| サイト構造 | 内部リンク、カテゴリ分け、階層構造 | サイト構造の最適化、導線改善 |
競合分析は、単なる模倣ではなく、自社の独自性を見出すプロセスです。情報の正確性と網羅性を追求し、常に最新の情報を提供することが重要となります。専門家による監修や、業界での認知度を高めることで、コンテンツの信頼性を向上させることができます。
被リンク獲得戦略も重要な差別化ポイントです。質の高いコンテンツを継続的に提供し、外部メディアでの露出を増やすことで、自然な形で被リンクを獲得できます。ユーザー体験の観点からは、読みやすさや操作性、高速な表示速度を追求し、サイト全体の魅力を高めることが求められます。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
まとめ
検索順位の低下は、一時的な損失ではなく、むしろWebサイト改善の機会と捉えるべきです。テクニカルな最適化、コンテンツの質の向上、競合分析を通じて、継続的に自社のプレゼンスを強化することが重要となります。
最終的に成功するSEO戦略とは、一時的な順位変動に惑わされることなく、常にユーザーに価値ある情報を提供し続けることなのです。
検索エンジンのアルゴリズムは常に進化し続けており、柔軟かつ計画的なアプローチこそが、長期的な検索順位の安定と向上をもたらすでしょう。