
マーケティングにおける購買行動とは、消費者が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連のプロセスを指します。この行動過程を分析し、体系化したものが購買行動モデルです。
かつてのマスメディア時代から、インターネットの普及によるWeb時代、そして現在のSNS時代へと移り変わる中で、さまざまな購買行動モデルが提唱されてきました。本記事では、購買行動の基本概念から各時代の代表的なモデル、そしてマーケティングへの具体的な活用方法まで、コンテンツマーケティングの視点から詳しく解説します。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
購買行動とは?モデルの基本と重要性

購買行動とは、消費者が商品やサービスを購入する際に取る一連の行動プロセスで、企業のマーケティング活動において、消費者の心理や行動を分析することは重要な要素となっています。
その過程はいくつかのフローに分けられ、「購買行動モデル」と呼ばれるフレームワークが多数存在しています。これらのモデルは時代とともに変化しており、マーケティングに従事する人々はそれらを活用して自社のマーケティング活動に役立てています。
購買行動の定義
マーケティングにおける購買行動とは、消費者がなんらかの商品やサービスを購入するプロセスで取る行動のことです。消費者が一つの商品やサービスを知ってから実際の購入に至るまでには、一定の心理状態や行動を経ています。
この一連の流れは分析され、さまざまなモデルとして提唱されてきました。これらは「購買行動モデル」と呼ばれ、企業のマーケティング活動で広く利用されています。
購買行動モデルを把握することで、消費者が商品やサービスと向き合う際の心理状態や検討フェーズにおける課題感がわかりやすくなります。その結果、課題における適切な対策を講じるためのヒントを得ることができるのです。
購買行動と消費者行動との違い
購買行動とよく似た言葉に「消費者行動」があります。いわゆるマーケティングの現場では、あまり厳密に区別されることがなく、意味としては購買モデルのことを指すことが多いでしょう。ただし、場合によっては区別して使われることもあるため、認識が混ざることのないよう注意が必要です。
特に経営学やマーケティング研究における文脈での「消費者行動」は、消費者が特定の商品へのニーズを想起したり、検討したりする状態よりも前の心理や行動についても対象に含まれています。具体的には、属する文化圏、社会階層、世代など、その消費者の消費行動に広い意味で影響を与えている要因について分析する研究分野となります。
また、購買行動モデルも、この消費者行動の研究で提唱された「五段階の購買行動プロセス」という考え方に深い関連性を持っています。
購買行動に影響を与える要因
購買行動には多くの要因が影響を与えています。まず個人的な要因として、年齢、性別、職業、経済状況などが挙げられます。たとえば、若年層はトレンドに敏感で新しい商品に興味を示しやすい傾向です。一方、年配の消費者は品質や実用性を重視する傾向があります。
また社会的要因としては、家族、友人、同僚などの周囲の人々からの影響が大きいと言えます。特にSNS時代においては、インフルエンサーやKOL(Key Opinion Leader)と呼ばれる人々の影響力は無視できません。彼らの発信する情報や評価が多くの消費者の購買決定に影響を与えています。
文化的要因も購買行動に大きく関わっています。国や地域の文化的背景、宗教、価値観などによって、同じ商品でも受け入れられ方が異なることがあります。グローバルなマーケティング戦略を展開する企業にとって、これらの文化的差異を理解することは非常に重要な課題となっているのです。
購買行動プロセスとマーケティング
購買行動プロセスを理解することは、効果的なマーケティング戦略を立てる上で不可欠です。消費者が商品を認知してから購入に至るまでの各段階において、適切なマーケティングアプローチを行うことが成功への鍵となります。
認知段階では、広告やプロモーションを通じて商品の存在を知らせることが重要です。興味・関心段階では、商品の特徴や利点を詳しく伝え、消費者の関心を高める必要があります。検索段階では、消費者が求める情報を簡単に見つけられるよう、SEO対策やコンテンツマーケティングが有効でしょう。
購入段階では、スムーズな購買体験を提供することが大切です。オンラインショップの使いやすさや実店舗の雰囲気など、購買環境の整備が重要となります。そして購入後の段階では、アフターサービスやフォローアップによって顧客満足度を高め、リピート購入や口コミにつなげることが求められます。
マスメディア時代の購買行動モデルの種類
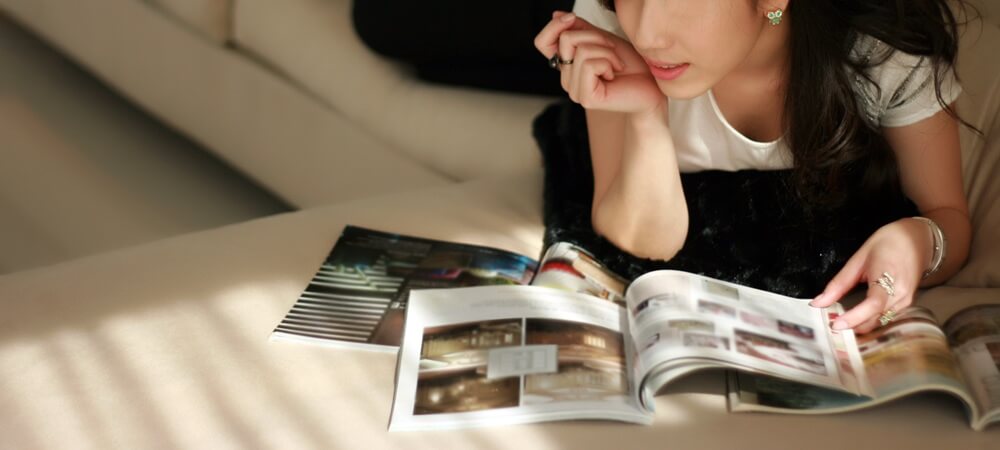
マスメディア時代の購買行動モデルは、テレビや新聞、雑誌などの従来型メディアが情報発信の中心だった時代に生まれました。この時代の特徴として、企業から消費者へ一方的かつ画一的に情報提供がなされていたことが挙げられます。
代表的なモデルとして1900年代初頭に提唱された「AIDA」や、そこから派生した「AIDMA」「AIDCAS」などがあります。これらのモデルは、現代においても購買行動を把握する際の基本的なフレームワークとして広く知られています。
AIDA(アイダ):最も古典的な購買プロセスの枠組み
AIDA(アイダ)は購買行動モデルにおいて最も古典的な理論として知られており、1900年代初頭にアメリカの広告人によって提唱されました。現在知られているさまざまな購買行動モデルの多くも、この理論を基礎として発展してきたという歴史的背景があります。
AIDAモデルの大きな特徴は、消費者が商品を認知してから購入するまでの行動を4つの段階に分けて分析している点にあります。このシンプルながら強力なフレームワークは、その後のマーケティング理論の発展に大きな影響を与えました。
| ステージ | 英語表記 | 日本語訳 | 内容 |
|---|---|---|---|
| A | Attention | 認知 | 広告によって商品やサービスを知る |
| I | Interest | 興味・関心 | 商品やサービスに対して興味を抱く |
| D | Desire | 欲求 | 商品やサービスを欲しいと感じる |
| A | Action | 行動 | 商品やサービスを購入する |
「Attention(認知)」では広告を通じて商品の存在を知り、「Interest(興味・関心)」で積極的な関心を持ち始めます。続く「Desire(欲求)」では「欲しい」という感情が生まれ、最終的に「Action(行動)」として実際の購買につながります。
AIDAモデルの価値は単純明快さにあります。誰にでも理解しやすい4ステップで購買プロセスを捉えることで、マーケティング施策の設計が容易になります。マスメディア時代の一方通行型コミュニケーションを前提としているため、現代では他のモデルと組み合わせて活用するとより効果的でしょう。
AIDMA(アイドマ):記憶の重要性を加えたモデル
AIDMA(アイドマ)は、AIDAモデルに続いて提唱された購買行動理論です。AIDAの基本構造を踏襲しながらも、「Memory(記憶)」という重要な要素が新たに加えられました。この変更によって、消費者の購買プロセスにおける記憶の役割が明確に位置づけられることになりました。
広告からの情報が必ずしも即座に購買行動に結びつくわけではなく、一時的な記憶を経て、その後の購入へと至るという現実的なプロセスを表現しています。つまり、商品やサービスの情報を消費者の記憶に強く印象づけることが、最終的な購買行動を促す上で不可欠だという考え方が反映されているのです。
| ステージ | 英語表記 | 日本語訳 | 内容 |
|---|---|---|---|
| A | Attention | 認知 | 広告によって商品やサービスを知る |
| I | Interest | 興味・関心 | 商品やサービスに対して興味を抱く |
| D | Desire | 欲求 | 商品やサービスを欲しいと感じる |
| M | Memory | 記憶 | 商品やサービスを覚える |
| A | Action | 行動 | 商品やサービスを購入する |
最初の「Attention(認知)」から「Desire(欲求)」までの段階はAIDAと同様ですが、「Memory(記憶)」という新たな段階では、消費者が商品情報を記憶に留め、後の購買判断の材料とします。記憶に残る広告を作ることの重要性が強調されています。
AIDMAモデルの特徴は、購買行動において消費者の記憶が果たす役割の重要性を明確にした点にあり、マスメディア広告が主流だった時代において、多くのマーケティング戦略の基盤となりました。
AIDCAS(アイドカス):確信と評価を含めた購買ステップ
AIDCAS(アイドカス)は、AIDMA(アイドマ)をベースに発展したモデルで、購買プロセスの理解をさらに深めた枠組みです。このモデルの大きな特徴は、「Conviction(確信)」と「Satisfaction(評価)」という二つの重要な段階が加えられた点にあります。これによって、消費者が単に欲しいと思うだけでなく、その商品やサービスが本当に必要だと確信するプロセスや、購入後の満足度評価までを包括的に捉えることが可能になりました。
「Conviction(確信)」の追加により、消費者の心理において「欲しい」という感情から「必要である」という確信への移行過程が明確化されました。高額商品や比較検討に時間のかかる商品では特に、この確信の段階が購買決定に大きな影響を与えるとされています。
| ステージ | 英語表記 | 日本語訳 | 内容 |
|---|---|---|---|
| A | Attention | 認知 | 広告によって商品やサービスを知る |
| I | Interest | 興味・関心 | 商品やサービスに対して興味を抱く |
| D | Desire | 欲求 | 商品やサービスを欲しいと感じる |
| C | Conviction | 確信 | 商品やサービスが必要であることを確信する |
| A | Action | 行動 | 商品やサービスを購入する |
| S | Satisfaction | 評価 | 商品やサービスを購入した結果について評価する |
「Conviction(確信)」段階では、消費者は購入に対して合理的な根拠を求めます。企業は詳細な商品情報や専門家の意見、ユーザーレビューなど、消費者の決断を後押しする情報提供が重要となるでしょう。
「Satisfaction(評価)」段階は、購入後の顧客体験と満足度に焦点を当てています。この評価は将来の購買行動や他者への推奨に大きく影響するため、企業にとって購入後のフォローアップやサポートが重要となります。
AIDCASモデルの重要な点は、購買プロセスを「認知から購入後の評価まで」という広い視点で捉えていることです。特に高額商品や慎重な検討を要する商品・サービスのマーケティングにおいて効果的なフレームワークとなります。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。
Web時代における購買行動モデルの種類の変化
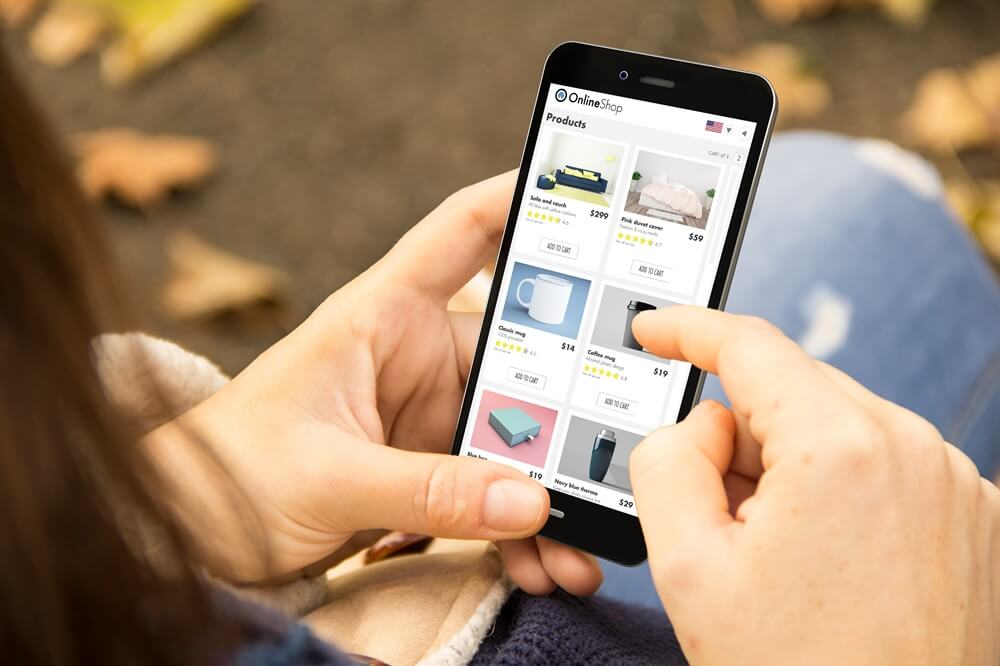
1990年代以降、インターネットが一般家庭にも急速に普及したことで、消費者の情報収集方法や購買行動に大きな変化が生じました。マスメディア時代のモデルが一方的な情報提供を基本としていたのに対し、Web時代のモデルではインターネットの特性を反映して、消費者自らが積極的に情報取得を行うことを基本に設計されています。
情報の非対称性が解消されるにつれ、「AISAS」や「DECAX」などの新しいモデルが登場しました。これらのモデルは、インターネット検索の普及によって消費者が自ら情報を調べる行動や、SNSやブログでの情報共有行動を取り入れた点が特徴的です。
AISAS(アイサス):検索と共有を重視したフレームワーク
AISAS(アイサス)は、2004年に電通が提唱した購買行動モデルで、インターネットの普及によって変化した消費者行動を反映したフレームワークとして広く知られています。このモデルの最大の特徴は、「Search(検索)」と「Share(共有)」という消費者の自発的な行動を取り入れた点にあります。
| ステージ | 英語表記 | 日本語訳 | 内容 |
|---|---|---|---|
| A | Attention | 認知 | 広告やメディアによって商品やサービスを知る |
| I | Interest | 興味・関心 | 商品やサービスに対して興味を抱く |
| S | Search | 検索 | 商品やサービスの情報をインターネットで検索する |
| A | Action | 行動 | 商品やサービスを購入する |
| S | Share | 共有 | 購入した結果についてインターネットで共有する |
従来のAIDMAモデルの「Memory(記憶)」がAISASでは「Search(検索)」に置き換えられ、消費者が能動的にインターネットで情報を探す行動を表しています。検索エンジンの利用やレビューサイトの閲覧など、購入前に調査する現代の消費者行動を反映しています。
また、「Action(行動)」の後に「Share(共有)」という段階が加わったこともポイントです。これは購入後に消費者がSNSやブログなどで体験や評価を共有する行動を示します。この共有情報が他の消費者の「Attention(認知)」や「Search(検索)」に影響を与えるという循環的な構造がWeb時代の特徴となっています。
DECAX(デキャックス):関係構築を取り入れた購買プロセス
DECAX(デキャックス)は、コンテンツマーケティングが広く浸透したことで生まれた購買行動モデルです。このモデルの特徴は、従来の広告から始まる購買プロセスではなく、消費者自らがWebメディアやニュースサイトなどから自発的に商品やサービスを発見することから始まる点にあります。
企業からの一方的な情報発信による認知ではなく、消費者の能動的な情報収集活動を出発点としている点が革新的でした。
| ステージ | 英語表記 | 日本語訳 | 内容 |
|---|---|---|---|
| D | Discovery | 発見 | Webメディアやニュースサイトで商品やサービスを発見する |
| E | Engagement | 関係構築 | 情報提供によって企業と消費者の関係構築を行う |
| C | Check | 確認 | 得られた情報の信頼性を確認する |
| A | Action | 行動 | 商品やサービスを購入する |
| X | eXperience | 体験と共有 | 商品やサービスを体験し、その結果についてインターネットで共有する |
「Discovery(発見)」では消費者が能動的に情報を探す中で商品に出会うプロセスを表します。次の「Engagement(関係構築)」は最も特徴的な要素で、企業が消費者に価値ある情報を継続的に提供することで信頼関係を構築していきます。
「Check(確認)」段階では、消費者が情報の信頼性を検証し、「Action(行動)」では実際の購買が行われます。最後の「eXperience(体験と共有)」で、購入後の体験を消費者がSNSなどで共有し、新たな消費者の「Discovery」につながる循環構造を形成します。
DECAXモデルは短期的な販売促進だけでなく、消費者との長期的な関係構築の重要性を示唆しています。
MOT(モット):購入の瞬間を捉える購買意思決定モデル
MOT(Moment of Truth)は、直訳すると「真実の瞬間」を意味し、消費者と企業が接点を持つ瞬間がマーケティングにおいて極めて重要であるという考え方です。この概念は1990年に刊行された『真実の瞬間―SAS(スカンジナビア航空)のサービス戦略はなぜ成功したか』という書籍の中で紹介され、多くのマーケティング担当者に影響を与えました。
同書では、スカンジナビア航空で働く従業員が搭乗者と接する「最初の15秒」が、企業やブランドに対するイメージを決定づけると述べられています。この短い時間内での印象が顧客満足度や企業評価を大きく左右するという視点は、多くの企業のサービス戦略に取り入れられるようになりました。
| MOTの種類 | 意味 | 内容 |
|---|---|---|
| FMOT (First Moment of Truth) | 最初の真実の瞬間 | 消費者が店舗を訪れて商品を選ぶ瞬間 |
| SMOT (Second Moment of Truth) | 2番目の真実の瞬間 | 消費者が商品を購入し使用する瞬間 |
| TMOT (Third Moment of Truth) | 3番目の真実の瞬間 | 消費者が商品の使用後に評価・共有する瞬間 |
| ZMOT (Zero Moment of Truth) | ゼロ番目の真実の瞬間 | 消費者が店舗訪問前にすでに購入商品を決めている瞬間 |
2011年にGoogleが提唱した「ZMOT」は、消費者が店舗訪問前にオンラインで情報収集し、すでに購入商品を決めているというWeb時代の行動を捉えた概念です。
MOTは時間経過の流れではなく「決定の瞬間」に焦点を当てており、この点が他の購買行動モデルとの違いです。特にZMOTはSEO対策やコンテンツマーケティングの重要性を裏付ける理論として活用されています。
SNS時代の最新購買行動モデルの種類
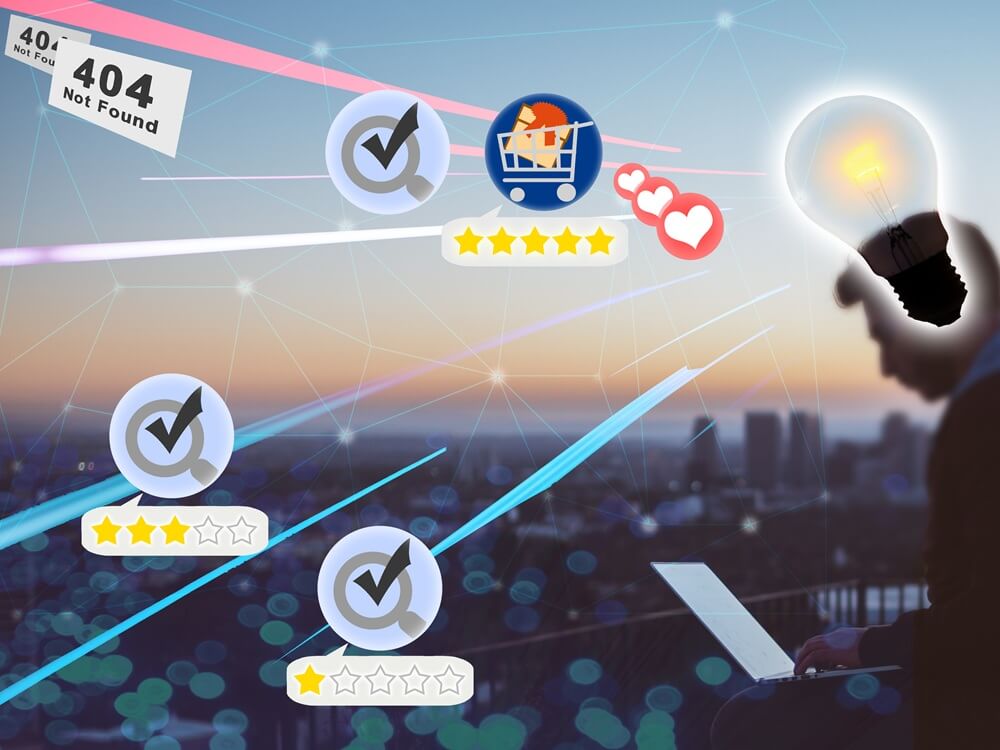
TwitterやInstagramをはじめとするソーシャルメディアが普及したことにより、消費者同士が相互に情報発信を行う文化が形成されました。2010年以降に提唱された購買行動モデルは、こうした現代の消費者心理を反映したものが多くなっています。
VISAS(ヴィサス):口コミと共感を中心とした購買心理
VISAS(ヴィサス)は、SNSによる発信を通して生まれる購買活動をモデル化した理論です。このモデルの最大の特徴は、消費者の購買欲求が生まれていない商品やサービスであっても、SNSでの口コミを偶発的に見かけることで共感や行動につながる点を捉えていることでしょう。
従来のモデルが「認知→興味→欲求」という流れを前提としていたのに対し、VISASでは「口コミ→影響→共感」という新しい流れを提示しています。
| ステージ | 英語表記 | 日本語訳 | 内容 |
|---|---|---|---|
| V | Viral | 口コミ | SNSでの口コミによって商品やサービスを知る |
| I | Influence | 影響 | 発信者や口コミによって消費者が影響を受ける |
| S | Sympathy | 共感 | 発信者や商品の情報に共感する |
| A | Action | 行動 | 商品やサービスを購入する |
| S | Share | 共有 | 購入した結果についてSNSで共有する |
「Viral(口コミ)」は企業の広告ではなく、SNS上のユーザーやインフルエンサーの投稿を通じて商品を知る経路を表します。「Influence(影響)」では投稿者の影響力によって消費者の心理が動かされ、「Sympathy(共感)」で投稿者の価値観や体験に共感することが購買意欲を高めます。「Action(行動)」の後の「Share(共有)」が次の消費者の「Viral(口コミ)」となり、循環構造を形成します。
VISASはSNSマーケティングの基本理論として広く知られています。企業は直接的な広告だけでなく、消費者同士の共感を生み出す価値提供や、共有したくなる体験設計が重要であることを示唆しているのです。
SIPS(シップス):共感から始まる消費者行動パターン
SIPS(シップス)は、SNSから得た情報への共感から消費者行動が始まることを提唱した購買行動モデルです。従来のモデルが企業からの情報発信を起点としていたのに対し、SIPSでは消費者が他者の情報や意見に共感することがプロセスの始まりとなります。
この「共感からの出発」という考え方は、SNS時代の消費者心理を的確に捉えたものと言えるでしょう。
| ステージ | 英語表記 | 日本語訳 | 内容 |
|---|---|---|---|
| S | Sympathize | 共感 | 発信者の情報や意見に共感する |
| I | Identify | 確認 | 得られた情報の信頼性を確認する |
| P | Participate | 参加 | 消費者が行動を起こすことで販促活動に参加する |
| S | Share & Spread | 共有・拡散 | 参加したことを共有・拡散する |
「Sympathize(共感)」段階では、SNSやブログで見た情報に共感することから行動が始まります。「Identify(確認)」では、共感した情報の信頼性を確認するプロセスが行われます。
「Participate(参加)」は単なる購買にとどまらず、ブランドのフォロー、キャンペーン応募、イベント参加など、さまざまな形態を含みます。最後の「Share & Spread(共有・拡散)」では、参加体験をSNSで共有し、新たな消費者の「共感」を生み出す循環構造を形成します。
SIPSモデルは特にブランディングやファン作りを重視する企業のマーケティング戦略に適したフレームワークと言えるでしょう。
ULSSAS(ウルサス):ユーザー投稿から拡散までの循環型モデル
ULSSAS(ウルサス)は、2019年にホットリンクによって提唱された最新の購買行動モデルです。このモデルの最大の特徴は、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)に着目し、一般ユーザーによる投稿が商品やサービスの認知につながるという現代的な消費者行動を捉えている点にあります。
| ステージ | 英語表記 | 日本語訳 | 内容 |
|---|---|---|---|
| U | UGC | ユーザー投稿コンテンツ | 消費者の投稿によって商品・サービスを知る |
| L | Like | いいね | SNSで気になる投稿に「いいね!」をする |
| S | Search 1 | SNS検索 | SNSで商品・サービスを検索する |
| S | Search 2 | Google/Yahoo!検索 | 検索エンジンで商品・サービスを検索する |
| A | Action | 行動 | 商品やサービスを購入する |
「UGC」は企業の広告ではなく一般ユーザーによる自発的な投稿を起点とし、「Like(いいね)」という軽いエンゲージメントが次の検索行動へとつながります。
現代的な特徴としては、「Search」が2段階に分かれている点です。「Search 1」ではSNS内で商品に関する投稿を検索し、「Search 2」では検索エンジンでより詳細な情報を収集します。これらを経て「Action(行動)」に至り、「Spread(拡散)」で体験を共有することで次の消費者の「UGC」となる循環構造を形成します。
ULSSASは直線的ではなく渦巻状の構造を採用しており、消費者行動の複雑性をより正確に表現しています。
購買行動モデルのマーケティングへの活用方法

購買行動モデルは、消費者が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連のプロセスを体系化したフレームワークです。これらのモデルをマーケティング戦略に活用することで、ターゲット顧客の心理や行動パターンに合わせた効果的なアプローチが可能になります。
時代とともに進化してきた購買行動モデルを実際のマーケティング活動にどのように落とし込むか、具体的な方法と効果について解説します。
顧客心理の各段階に合わせた効果的なアプローチ
購買行動モデルの最大の利点は、消費者の購買プロセスを段階別に分解して可視化できる点にあります。各段階における消費者の心理状態や行動特性を理解することで、それぞれに最適なマーケティング施策を展開できるようになります。
| 購買段階 | 対応するマーケティング施策 | 具体例 |
|---|---|---|
| 認知 | ブランド認知拡大施策 | テレビ CM、Web 広告、SNS 広告 |
| 興味・関心 | 詳細情報提供 | 商品紹介ページ、コンテンツマーケティング |
| 検索 | SEO 対策、リスティング広告 | キーワード対策、検索連動型広告 |
| 欲求・検討 | 比較訴求、レビュー活用 | 競合比較表、ユーザーレビュー掲載 |
| 購入 | 購入障壁低減 | 簡易決済、送料無料施策 |
| 共有・拡散 | 口コミ促進 | SNS シェアボタン、レビュー投稿特典 |
認知段階ではマス広告やターゲティング広告が効果的で、興味・関心段階では詳細な商品情報提供が重要です。検索段階ではSEO対策が鍵となり、欲求・検討段階では競合比較やレビュー活用が有効になります。
購入段階では購買プロセスの簡略化が重要で、共有・拡散段階では顧客の情報発信を促進する仕組みが大切です。
カスタマージャーニーマップとの連携
購買行動モデルの理解を深めるには、カスタマージャーニーマップとの連携が効果的です。理論的フレームワークに具体的な顧客体験の視点を加えることで、実効性の高い戦略を構築できます。
| 購買行動ステージ | カスタマージャーニーの要素 | 検討すべきポイント |
|---|---|---|
| 認知 | タッチポイント、情報源 | どこで最初に知るか、何がきっかけになるか |
| 興味・検索 | 情報収集行動、疑問点 | どんな情報を求めるか、どこで調べるか |
| 検討 | 意思決定要因、障壁 | 何を比較するか、購入を迷う理由は何か |
| 購入 | 購買経路、決済方法 | どこで買うか、どうやって支払うか |
| 使用・共有 | 使用体験、共有行動 | どう使うか、どこで感想を共有するか |
カスタマージャーニーマップを作成する際は、まず自社製品やサービスに関連する購買行動モデルを選定します。たとえばSNSでの口コミが重要な商品であれば、VISASやULSSASモデルが適しているでしょう。選定したモデルの各段階に沿って、顧客の具体的な行動や感情、タッチポイントを洗い出していきます。
このプロセスでは、実際の顧客インタビューやアンケート、Web解析データなどを活用して、仮説ではなく実データに基づいたマップを作成することが重要です。特に、各段階での顧客の疑問点や不満、障壁を明確にすることで、改善すべきポイントが見えてきます。
完成したカスタマージャーニーマップは、マーケティングチームだけでなく、商品開発や顧客サポート、営業部門など社内の様々な部署で共有することで、顧客中心の組織文化の醸成にも役立ちます。
デジタルマーケティング施策への落とし込み方
購買行動モデルを理解したら、各段階に対応したデジタルマーケティング施策を設計し、適切なKPIを設定することが重要です。
| 購買段階 | デジタルマーケティング施策 | KPI例 |
|---|---|---|
| 認知 | ディスプレイ広告、YouTube広告、SNS広告 | 認知度、リーチ数、動画視聴数 |
| 興味・検索 | SEO対策、コンテンツマーケティング | サイト訪問者数、検索順位、PV数 |
| 検討 | リターゲティング広告、メールマーケティング | 滞在時間、資料請求数、見積もり依頼数 |
| 購入 | カート最適化、LPO、クーポン配布 | コンバージョン率、購入単価、ROI |
| 共有・拡散 | レビュー依頼、SNSキャンペーン | 口コミ投稿数、シェア数、エンゲージメント率 |
認知段階ではディスプレイ広告やYouTube広告を活用し、ブランド認知度やリーチ数をKPIとします。興味・検索段階ではSEO対策とコンテンツマーケティングで検索上位表示を確保し、訪問者数の向上を目指します。
検討段階ではリターゲティング広告やメールマーケティングで詳細情報を提供し、購入段階ではカート最適化やLPOでコンバージョン率を高めます。共有・拡散段階ではレビュー依頼やSNSキャンペーンで次の顧客獲得につなげましょう。
施策全体では一貫性のある顧客体験を提供することが重要です。
まとめ
購買行動モデルは、消費者が商品やサービスを購入するまでの心理や行動を段階的に捉えたフレームワークです。マスメディア時代のAIDA、AIDMA、AIDCASから始まり、Web時代にはAISAS、DECAX、MOTへと発展し、現在のSNS時代ではVISAS、SIPS、ULSSASといった新たなモデルが登場しています。
これらのモデルは時代とともに進化していますが、その根底には「認知から行動へ」という基本的な考え方が共通しています。
効果的なマーケティング戦略を構築するためには、自社の商品やサービス、ターゲット顧客に適した購買行動モデルを選び、各段階に合わせた施策を展開することが重要です。カスタマージャーニーマップとの連携やデジタルマーケティング施策への落とし込みを通じて、一貫性のある顧客体験を提供しましょう。
記事制作数1億本以上、取引社数5,300社超の実績
豊富な制作実績と蓄積されたノウハウで、成果につながるコンテンツマーケティングを実現。
記事制作のみならず戦略設計から運用支援まで、ワンストップで対応します。













